人気テーマ

公開シンポジウム「今、大学教育を考える-職業との関連から-」
2013/06/03 タグ: 編集部より
角方正幸(リアセックキャリア総合研究所所長/「就業力の広場」責任者)
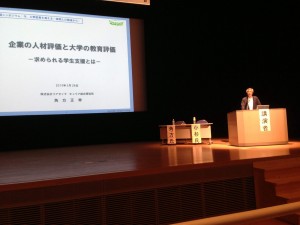 日本高等教育学会第16回大会において、「今、大学教育を考える-職業との関連で-」と題する公開シンポジウムが5月26日に行われた。私は報告者の1人として登壇し、①大学教育と職業との関連についての総括的な概念整理とその実態について(金子元久筑波大学教授)、②第三段階教育という観点からの大学教育と職業との関係の再検討(吉本圭一九州大学教授)に続いて、③企業側の視点に立った実践的な就業力育成等の現状と課題についての報告を行った。
日本高等教育学会第16回大会において、「今、大学教育を考える-職業との関連で-」と題する公開シンポジウムが5月26日に行われた。私は報告者の1人として登壇し、①大学教育と職業との関連についての総括的な概念整理とその実態について(金子元久筑波大学教授)、②第三段階教育という観点からの大学教育と職業との関係の再検討(吉本圭一九州大学教授)に続いて、③企業側の視点に立った実践的な就業力育成等の現状と課題についての報告を行った。
以下は、その報告の一部要約である。
大学で良い成績を修めることが就職に結び付かない
報告のタイトルは「企業の人材評価と大学の教育評価の不一致」とした。
配布資料「企業の人材評価と大学の教育評価の不一致」
http://www.riasec.co.jp/hiroba/sys/wp-content/uploads/2013/05/paper20130526web.pdf
企業が評価する人材と大学での成績との間にはギャップが存在している。例えば「成績の優秀な学生がなかなか教員試験に受からない。反対に成績下位の学生が教員試験には受かる。教員としてこれをどう考えたらいいか」と悩む教育学部の教員がいる。また例えばある工学部で、学生の大学での成績とインターンシップ先の企業による評価点を調査し、ほとんど相関がないという結果を得た。
つまり、学部を問わず、大学で良い成績を修めても就職に結び付かない。――このような矛盾があっては、大学生が主体的に学びに取り組まないのも無理もない。
人材モデルの可視化
実践的な就業力育成支援は、このギャップを解消する方向性をもつことが望ましい。そのためにはまず、人材モデルの可視化が必要となる。大学教育の当事者が企業の求める人材像を把握し、自らの人材育成(教育)目標を明確にするためである。
企業の求める人材像を把握するための資料としては、リアセックが実施した「人材ニーズ調査」が参考になる。対人・対自己・対課題の基礎力のうち、企業が重視しているのは対人基礎力であることなどがわかる。
どのような能力を育成するのかを可視化し、教育目標を設定するには、リアセック・河合塾共同開発の基礎力測定テスト「PROG」を利用するのが1つの方法である。
「PROG」は、基礎力評価の客観性を高めるために、モデル人材(学生の「お手本」となるような社会人)への調査を行っている。モデル人材が保有している能力は、学生に育成されるべきであると考えることができる。例えば「グローバル人材」であればストレスマネジメント、人脈形成、親しみ易さのコンピテンシーが重要であり、「小学校教諭」は信頼構築、主体的行動、実践行動のコンピテンシーが重要というふうに可視化される。
最後に、私が数多くの大学で経験してきたことを踏まえ、実践的な就業力の育成ポイントを8箇条にまとめた。詳しくは、以下の資料を参照されたい。
投影資料「企業の人材評価と大学の教育評価の不一致」
http://www.riasec.co.jp/hiroba/sys/wp-content/uploads/2013/05/slide20130526web.pdf
なお、当日は時間の関係から参加者からの質問に回答する時間が限られてしまった。そのときの代表的な質問については、機会を見つけてこの場でお答えできたらと考えている。


